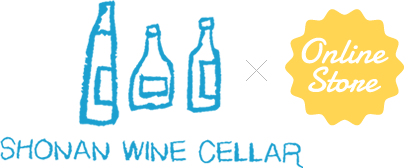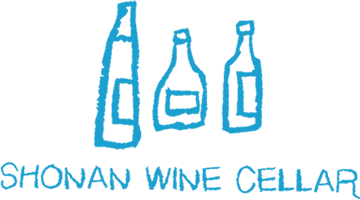フランク・コーネリッセン

【インポーター情報】
『もはや鬼才でもなんでもなく、ブドウ以外の何物も使用することなく、エトナという土地の個性、ポテンシャルを余すことなく液体に乗り移らせつつも、実に普遍的な味わいのワインを造り出している』
この仕事をやっていて、一度持たれてしまったイメージを覆すことというのは、非っ常に難しいことなんだと痛感させられたのは、やはりフランクのワインを通してということになるのでしょうか。
デビュー当初は、ワイン界のアナーキスト扱いだった彼も、いつの間にかエトナを代表するテロワリスト(Terroirist、実際には存在しない言葉ですが、テロワールを体現する人という意味の言葉だと何となく認知されているような…。間違ってiが抜けちゃったら、テロリストになっちゃいますね…。)の1人として、世界中で認識される存在となっています。なにせ、ワインをリリースさせる前からの付き合いですし、初期の頃は生産量の半分くらいを買っていましたので(まー、我ながら良くやったと思います…)、彼の今現在のエトナというゾーンとワイン界で築き上げた立ち位置には、非常に感慨深いものがあります。
とはいえ、ワイナリー発足当初から今現在に至るまでに、基本理念とそれに従った畑&セラーでの作業の仕方が大きく変わったということは一切なく、本当に微調整程度の積み重ねだけが、発足当初と現在のワインの間にある大きな味わいの差を生み出しています。
テロワールを体現したワインであること、それを実現するためには、農法的にも極めてナチュラルであるべきで、基本ボルドー液さえも使わず、完熟したブドウを用い、白、赤、ロゼの区別なく乳酸発酵が完全に終了するまで皮や種と一緒にして醸し状態とし、ブドウ由来以外の風味がワインに付くことを嫌い、木樽は用いず、醸造&ボトリングの際にも酸化防止剤を一切使用しない…この辺りが不変の理念ということになるかと。
エトナ山の麓で2001年にワインを造り始めた当初、彼が理想目標として掲げたワインは、“(火山)岩が液体化したかのようなワイン”でした。果実味などという、分かりやすい味わいなど全くなく、ミネラルだけで構成されている、完全に醗酵&熟成(酸化と熟成の境目を狙った)しきったワイン…マグマ1(2001)は、デビュー作にして、当時のフランクの理想形を具現化したようなワインで、初っ端から自分が思い描いているものを実現させられるセンスに驚愕したのを記憶しています。本当に難解なワインでしたし、友達造り手の間でも賛否両論が激しく飛び交いましたっけ…う~ん、それも懐かしい!!